学校事務の仕事に興味があるものの、「きついのでは?」「楽すぎって本当?」と気になっていませんか。職員として学校運営を支える重要な仕事であるものの、「給料が安い」「休めない時期がある」「大変なことが多い」といった声もあり、「やめとけ」と言われることもあります。一方で、公務員としての安定性やワークライフバランスの良さから「ホワイトな職場」と評価され、なぜ人気があるのか気になる人も多いでしょう。
この記事では、学校事務の仕事内容や難易度、楽すぎと言われる理由、職員になるにはどうすればいいのか、さらに本当に「やめとけ」と言われるような仕事なのかを詳しく解説します。学校事務に向いてる人の特徴や、給料・待遇の実態まで幅広く紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
- 学校事務の仕事内容と大変なこと
- なぜ楽すぎと言われるのか本当の実態
- 学校事務職員になるには何が必要か
- 給料や休めない時期などの働く環境
学校事務の仕事はきつい?実態を徹底解説
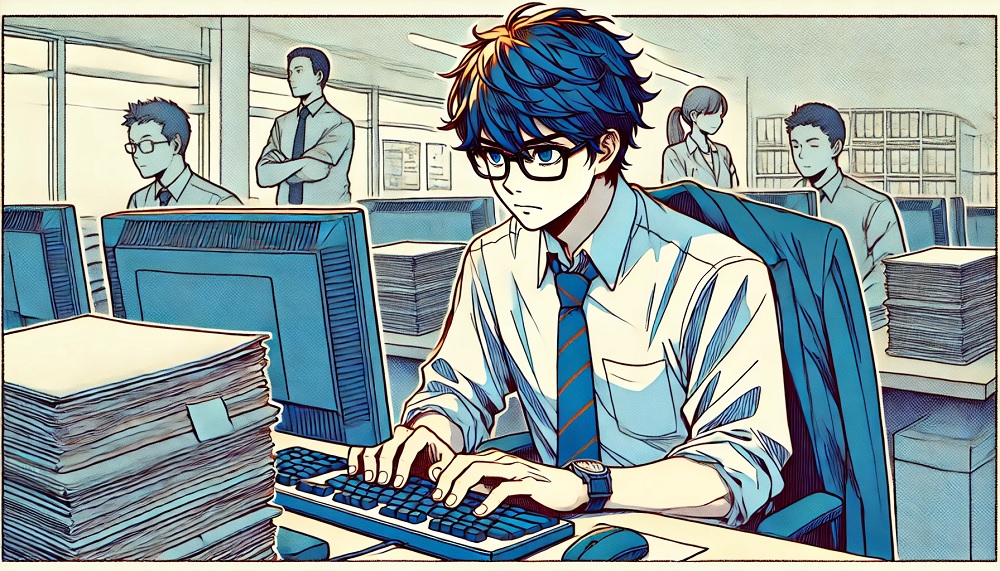
- 仕事内容と大変なこと
- つらいと感じるポイントと対処法
- 休めないって本当?
- 給料は安い?年収や待遇の実態
- なぜ「楽すぎ」と言われるのか?
仕事内容と大変なこと
学校事務の仕事は、主に「学校全体の運営を支えること」が役割です。具体的には、庶務・人事労務・会計・教務といった業務を担当し、教員や生徒がスムーズに学校生活を送れるようにサポートします。一見すると一般的な事務職と変わらないように思えますが、学校特有のルールやスケジュールに沿って動く必要があるため、独自の業務も多いのが特徴です。
まず、庶務関係の業務では、来校者や保護者の窓口対応、電話・メールの応対、各種証明書の発行などを行います。保護者とのやりとりが発生することもあり、時にはクレーム対応を求められることもあります。生徒のトラブルに関する相談を受ける場面もあり、コミュニケーション力が求められる仕事です。
次に、人事労務関連の業務として、教職員の給与計算や福利厚生の手続き、出張時の旅費精算などを担当します。これらは学校の運営に不可欠な業務であり、正確性が求められます。特に給与や福利厚生に関する業務では、一つのミスが大きなトラブルにつながることもあるため、慎重な作業が必要です。
また、会計関係の業務も重要な仕事の一つです。学校の予算管理や、備品・教材の発注・支払い、授業料や給食費の徴収などを行います。特に公立学校では、公費の適正な使用が求められるため、細かい経理作業が発生することが多く、事務処理能力が必要になります。加えて、業者とのやり取りも多く発生するため、対外的な折衝能力も求められます。
さらに、学校事務ならではの教務関連業務もあります。入学や卒業、転校の手続き、成績処理、教材の手配、生徒募集に関する業務など、学校の運営に深く関わる業務です。学校の年間行事に沿って動くことが多く、繁忙期と閑散期の差が激しいのも特徴です。特に、入学試験や卒業式の時期には多くの書類業務が発生し、業務が集中しやすい点が大変な部分です。
このように、学校事務の仕事は幅広く、多岐にわたる業務をこなす必要があります。そのため、一つの分野に特化するのではなく、幅広いスキルが求められる仕事といえるでしょう。
つらいと感じるポイントと対処法

学校事務の仕事は安定している一方で、つらいと感じるポイントも多くあります。学校独自の環境が影響することもあり、一般的な事務職とは異なる悩みが発生することが特徴です。ここでは、よく挙げられるつらいポイントと、それに対する対処法を解説します。
まず一つ目は、業務の幅が広すぎることです。学校事務は、庶務・会計・人事・教務など、さまざまな業務を担当するため、一つの仕事に集中するのが難しい環境です。特に少人数の学校では、一人の事務職員が複数の業務をこなさなければならず、仕事の負担が大きくなります。また、年度末や新年度の開始時期など、業務が立て込む時期には特に忙しくなり、残業が増えることもあります。
この問題への対処法としては、業務の優先順位を明確にすることが重要です。全ての業務を完璧にこなそうとすると負担が大きくなるため、特に期限が厳しいものから優先的に処理するようにしましょう。また、効率的に作業を進めるためのスケジュール管理や、定型業務のマニュアル化を進めることも効果的です。
二つ目は、保護者や地域住民との対応が大変なことです。学校事務は窓口業務を担当するため、保護者からの問い合わせや苦情対応を行うことがあります。時には、理不尽な要求を受けることもあり、精神的な負担が大きくなることも少なくありません。特に、生徒間のトラブルや部活動の騒音問題など、対応が難しいケースもあるでしょう。
このような問題への対処法としては、感情的にならず冷静に対応することが重要です。保護者や地域住民の意見を真摯に受け止めつつも、学校のルールや方針に基づいて適切に対応することが求められます。また、必要に応じて教員や管理職と連携を取りながら、対応を進めることも大切です。
三つ目は、職場の人間関係が複雑なことです。学校事務は、事務職員同士だけでなく、教員や校長、さらには教育委員会との関係もあります。事務職員は、教員とは異なる立場のため、学校内での立ち位置が微妙になりやすく、場合によっては軽視されることもあります。また、学校ごとに雰囲気が異なるため、異動が発生すると新しい環境に適応するのが大変に感じることもあります。
この問題を解決するには、職場内のコミュニケーションを意識的に取ることが重要です。業務上の連携をスムーズにするためにも、教員や管理職と良好な関係を築く努力が求められます。また、自分の仕事に対する理解を深めてもらうためにも、業務の重要性を適切に伝えることが大切です。
このように、学校事務にはさまざまなつらい点がありますが、適切な対処法を実践することで、負担を軽減することができます。仕事の進め方や周囲との関係性を工夫することで、より働きやすい環境を作っていくことが重要です。
休めないって本当?

学校事務の仕事は基本的に公務員であり、土日祝日が休みの完全週休二日制が多いですが、実際には「休みにくい」と感じることもあります。特に、学校行事や業務の繁忙期には休日出勤が発生することもあり、完全にカレンダー通りに休めるとは限りません。
まず、公立学校の事務職員は、運動会や入学試験、卒業式などの学校行事に関わる業務を担当することがあり、これが土日や祝日に実施される場合、出勤が必要になります。ただし、多くの自治体では振替休日や代休制度が整っているため、後日休みを取ることが可能です。
また、有給休暇については、業務の調整ができれば取得しやすい環境といえます。一般企業に比べると、学校事務の仕事は年間スケジュールがある程度決まっているため、計画的に有給を取得することができます。しかし、少人数で業務を回している学校では、休むことで他の職員に負担がかかるため、気を遣って休みにくいと感じる人もいるでしょう。
結果として、学校事務の仕事は「完全に休めないわけではないが、時期によっては休みづらいことがある」といえます。休みを確保するためには、繁忙期を避けて計画的に休暇を取得する工夫が必要になります。
給料は安い?年収や待遇の実態

学校事務の給料は「公務員としては安い」「民間企業の事務職と比べると悪くない」と言われることが多いです。特に公立学校の事務員は地方公務員に分類されるため、自治体ごとの給与体系が適用されます。そのため、企業の事務職と比べると比較的安定している一方で、他の公務員職種よりも年収が低いことがあるのが特徴です。
まず、公立学校の事務員の給与について見ていきましょう。令和3年の東京都のデータによると、学校事務の平均給与月額は約46万円で、年収換算すると約760万円となります。しかし、これはあくまで平均であり、勤続年数が長い職員の給与も含まれています。初任給は約22万円前後のケースが多く、昇給はあるものの、他の公務員職種と比べて大幅に給与が上がることは少ない傾向があります。また、地域によっても給与水準に差があり、都市部では比較的高めの水準ですが、地方では年収400万〜500万円程度のこともあります。
一方、私立学校の事務員は、公務員ではなく民間企業の従業員と同じ扱いになります。給与は学校ごとの規定に依存するため、公立学校よりも幅が広いです。大手の私立学校や大学では、公務員と同程度かそれ以上の給与を得られる場合もありますが、小規模な私立学校では年収が低めに設定されていることもあります。特に、契約社員や派遣社員として働く場合は、さらに給与水準が下がることが多いため、正社員としての採用を目指すことが重要です。
待遇については、公立学校の事務員は地方公務員として、基本的な福利厚生や各種手当が整っています。例えば、住宅手当・扶養手当・地域手当などが支給されるほか、ボーナス(期末・勤勉手当)も一般の地方公務員と同様に支給されます。有給休暇や産休・育休も取得しやすい環境にあり、ワークライフバランスを重視したい人には適した職種と言えるでしょう。
ただし、公務員であるため副業が禁止されており、収入を増やしたいと考えたときに自由度が低い点はデメリットになります。また、定期的な異動があるため、慣れた職場で長く働き続けることが難しいケースもあります。
私立学校の場合は、福利厚生は学校ごとに異なりますが、公立と比べて手当が少ないことが多いです。さらに、学校の経営状態によっては、給与カットやボーナス削減が行われるリスクもあるため、安定性という点では公立の学校事務に劣ることがあります。
総じて、学校事務の給与は「公務員としては安め」「民間の事務職と比べると安定しているが給与水準には差がある」と言えます。特に、収入を重視する場合は、勤務地(都市部か地方か)や公立・私立の違いをしっかり確認した上で、適切な職場を選ぶことが重要になります。
なぜ「楽すぎ」と言われるのか?
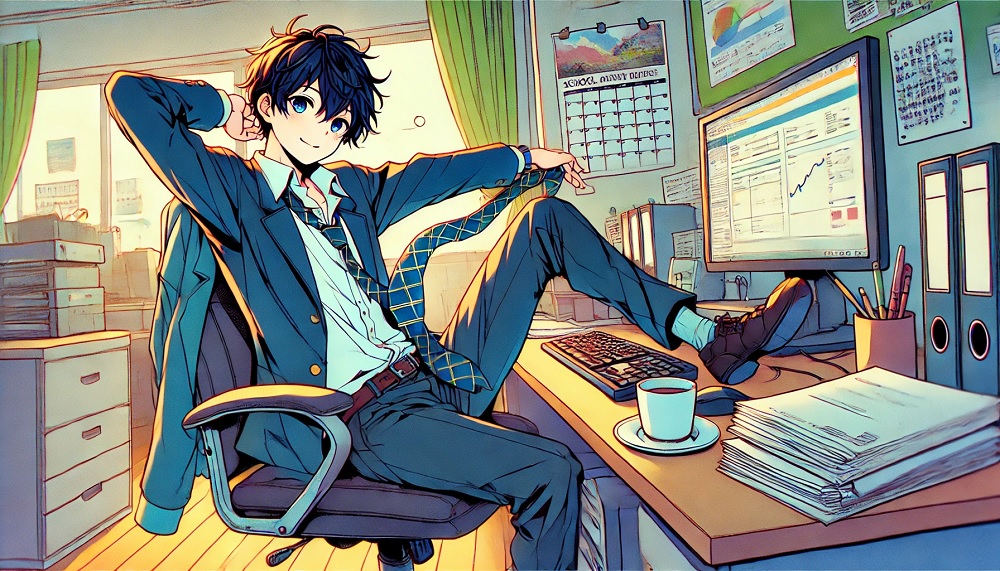
学校事務の仕事は、「楽すぎ」と言われることがあります。その理由として、残業が少ないことや、仕事内容がパターン化しやすいこと、肉体的負担が少ないことなどが挙げられます。ただし、これがすべての学校に当てはまるわけではなく、職場環境や時期によっては忙しくなることもあるため、一概に「楽な仕事」とは言えません。
まず、学校事務が「楽すぎ」と言われる最大の理由は、残業が比較的少ないことです。一般企業の事務職と異なり、学校は基本的に決まった時間で業務が進むため、急な残業が発生しにくい傾向にあります。学校のスケジュールがあらかじめ決まっているため、繁忙期と閑散期の差はあるものの、突発的な業務が発生することは少なく、計画的に仕事を進めやすいのが特徴です。
また、仕事内容がパターン化しやすい点も「楽すぎ」と言われる理由の一つです。学校事務の仕事は、入学・卒業、成績処理、教材発注、会計処理など、毎年ほぼ同じスケジュールで業務が進みます。そのため、経験を積むほど業務の流れが分かりやすくなり、効率的に仕事を進められるようになります。一方で、ルーティンワークが多いため、単調な作業が続くことに退屈さを感じる人もいるかもしれません。
さらに、肉体的な負担が少ない点も「楽」と言われる要因です。一般企業の営業職や工場勤務などと比べると、学校事務はデスクワーク中心の仕事が多く、体力的な負担が少ない職種といえます。また、夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中は、学校全体の業務量が減るため、比較的落ち着いて働けることもあります。
ただし、学校事務の仕事が「楽すぎ」とは言い切れない側面もあります。特に、公立の学校事務では業務範囲が広く、一人にかかる負担が大きくなることがあるため、決して楽な仕事ばかりではありません。特に小規模な学校では、少人数で事務作業を回す必要があり、庶務・人事・会計・教務のすべてを一人で担当することもあります。そうなると、業務の負担は大きくなり、忙しさを感じることも多くなります。
また、人間関係やクレーム対応が大変という側面もあります。学校事務は、保護者や地域住民との窓口になることが多いため、クレームや苦情の対応をすることもあります。特に、生徒間のトラブルや学校の運営に関する問題について保護者から厳しい意見を受けることもあり、精神的に負担を感じる場面もあるでしょう。
このように、「楽すぎ」と言われる理由は、残業が少ないことや業務がパターン化しやすいことなどが挙げられますが、実際には業務範囲の広さや対人対応の大変さもあり、一概に楽な仕事とは言えません。学校や時期によって業務量の違いがあるため、働く環境によって仕事の負担は大きく変わるのが学校事務の特徴といえるでしょう。
学校事務の仕事はきつい?向いている人の特徴

- 難易度は?採用試験や公務員じゃない真相
- 職員になるには?必要なスキルや資格
- ホワイト?それともブラック?
- なぜ人気?勝ち組と言われる理由
- やめとけと言われる理由と辞めたいと感じた時の選択肢
難易度は?採用試験や公務員じゃない真相
学校事務の仕事に就くための難易度は、公立と私立で大きく異なります。公立学校の事務職は地方公務員であり、公務員試験を受ける必要があります。一方、私立学校の事務職は民間企業の職員と同じ扱いになり、試験というよりは一般的な就職・転職活動と同じ流れで採用されます。
まず、公立学校の事務職員になるためには、各自治体が実施する公務員試験に合格する必要があります。多くの自治体では「学校事務職」という専門の採用枠が設けられていますが、東京都のように一般事務職として採用され、配属先の一つとして学校事務が選ばれる場合もあります。試験の内容は教養試験(一般知識・文章理解・数的推理など)、論文試験、面接試験が主であり、行政事務職よりも専門性の高い試験を課す自治体もあります。
試験の倍率は自治体によって異なりますが、一般的に5倍〜10倍程度で推移しており、決して簡単ではありません。ただし、行政職の公務員試験と比べると専門試験がない場合が多く、勉強する範囲が比較的狭いため、戦略的に勉強すれば合格の可能性は高まります。
一方で、私立学校の事務職は、公務員試験のような統一された試験はなく、一般企業と同じ採用プロセスを経ることになります。求人情報サイトや学校の公式ホームページで募集を探し、履歴書や職務経歴書を提出して選考を受けます。採用試験として、筆記試験(一般常識・作文)や面接を実施する学校もありますが、難易度は学校によって異なります。また、学校によっては契約社員や派遣社員として採用されることもあり、正社員登用の有無や待遇については事前に確認することが重要です。
「学校事務=公務員」と思われがちですが、私立学校の事務職は公務員ではありません。 そのため、公務員特有の安定した雇用や待遇が得られない場合もあります。特に、学校の経営状況が厳しくなると給与カットや契約終了の可能性もあるため、公立と私立の違いをしっかり理解しておくことが重要です。
職員になるには?必要なスキルや資格
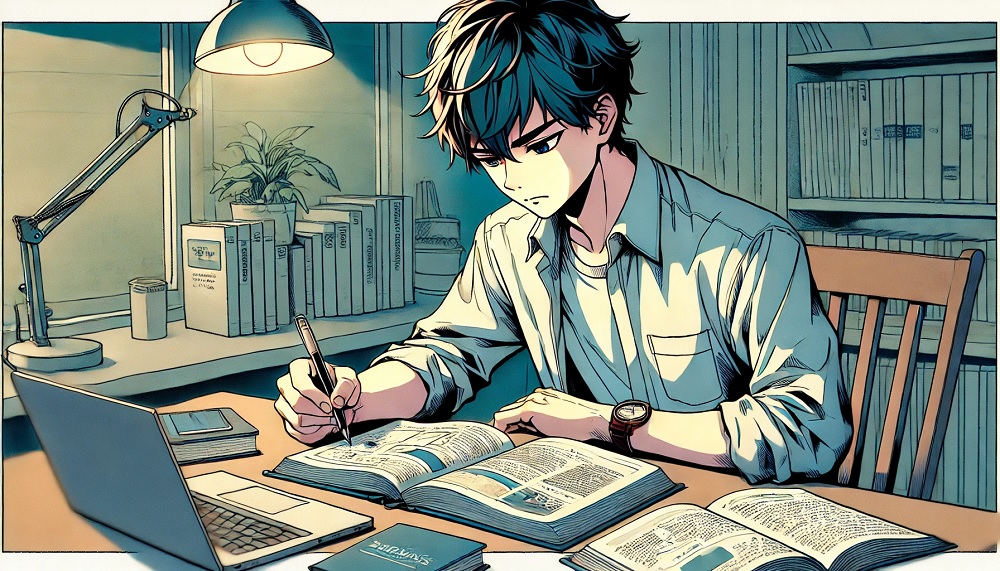
学校事務の職員になるために、必須の資格はありません。特に公立学校の事務職は、公務員試験に合格すれば、特別なスキルがなくても採用されることが可能です。しかし、実際に仕事をスムーズに進めるためには、一定のスキルが求められます。
まず、パソコンスキルは必須といえます。学校事務の仕事では、WordやExcelを使用した文書作成・表計算が日常的に行われます。特に、Excelを使ったデータ管理や計算業務が多いため、関数やピボットテーブルの基本的な知識があると仕事がスムーズに進められます。また、最近ではGoogleドキュメントやスプレッドシートを活用する学校も増えているため、これらのツールの操作に慣れておくと有利です。
次に、コミュニケーション能力も重要です。学校事務は教員や保護者、業者など多くの人と関わる仕事です。そのため、相手の意図を正確に理解し、適切に対応できる能力が求められます。特に、保護者対応ではトラブルになることもあるため、冷静に対応する力や、説明をわかりやすく行う力があると役立ちます。
さらに、事務処理能力と正確性も求められます。学校の会計業務や成績管理など、ミスが許されない業務が多いため、細かい作業を丁寧に進める力が必要です。公立学校の事務職は地方自治体のルールに従って業務を行うため、公的な書類の作成や予算管理の経験があると、よりスムーズに業務を進めることができます。
また、学校運営に関する知識も役立ちます。特に私立学校の事務職では、生徒募集や入試の運営に関わることもあるため、学校経営やマーケティングの知識があると重宝されるでしょう。学校の特徴や教育方針を理解し、それに沿った業務を遂行する姿勢も重要です。
このように、学校事務の仕事に就くためには、特別な資格は不要ですが、パソコンスキル、コミュニケーション能力、事務処理能力などが求められます。実際に仕事をする際に困らないよう、事前にスキルを磨いておくと良いでしょう。
ホワイト?それともブラック?

学校事務の仕事は「ホワイトな職場」と言われることが多いですが、一方で「ブラックな面もある」と感じる人もいます。その理由は、働く環境によって大きく異なるからです。公立学校と私立学校、また学校の規模や職場の人間関係によって、働きやすさが変わることを理解しておくことが大切です。
まず、公立学校の事務職はホワイト寄りの環境が多いといえます。公務員であるため、勤務時間が厳密に管理されており、残業は比較的少なめです。また、給与や福利厚生も地方公務員としての待遇が受けられるため、安定した収入が期待できます。さらに、年次有給休暇や育休・産休の取得もしやすく、ワークライフバランスを取りやすい職場といえるでしょう。
しかし、ブラックな側面もあります。特に異動が頻繁にあることが、公立学校事務職の特徴です。数年ごとに異なる学校に配属されるため、せっかく職場の環境に慣れても、新しい人間関係を築き直す必要があります。また、学校によっては教員との関係が難しく、事務職員が軽視されるケースもあります。
一方、私立学校の事務職は学校ごとに労働環境が異なるため、ホワイトかブラックかの判断が難しいです。一般的に、私立学校は公立と比べて給与が高めに設定されていることが多く、業務の裁量も大きい傾向があります。しかし、経営状況が不安定な学校では、給与の遅配や業務量の増加が発生することもあります。特に、生徒募集が厳しい学校では、業務負担が増えたり、人員が削減されたりするリスクがあるため、注意が必要です。
また、ブラックな要素として、人間関係のストレスが挙げられます。学校事務は教員・保護者・業者と関わることが多く、クレーム対応やトラブル処理に追われることもあります。特に、学校運営の方針によっては、事務職員の負担が増えるケースもあるため、事前に職場の雰囲気を確認することが重要です。
このように、学校事務は「ホワイトな要素」と「ブラックな要素」が混在する職場です。安定した職場を求める場合は、公立学校の事務職が向いているでしょう。一方で、給与や業務の自由度を求める場合は、私立学校の事務職を検討するのが良いでしょう。
なぜ人気?勝ち組と言われる理由
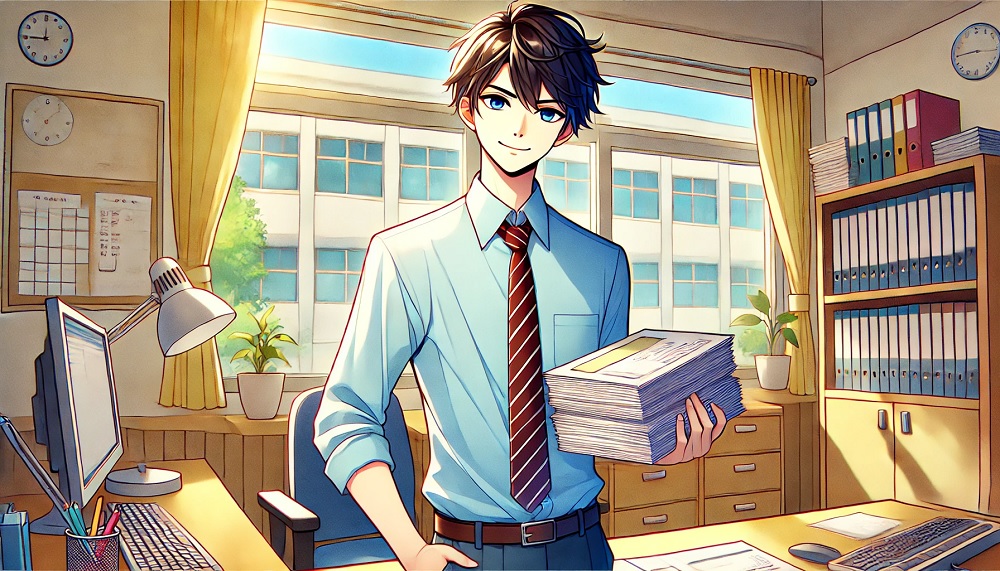
学校事務の仕事は「安定している」「ワークライフバランスが取りやすい」といった理由から人気があり、「勝ち組」とも言われることがあります。特に公立学校の事務職は地方公務員に分類されるため、長期的に安定した収入と雇用を確保できることが魅力です。ここでは、なぜ学校事務が人気なのか、勝ち組とされる理由を詳しく解説します。
まず第一に、安定した雇用と収入が挙げられます。公立学校の事務職は地方公務員であるため、景気の影響を受けにくく、リストラの心配がほとんどありません。また、給与体系が自治体ごとに決まっており、民間企業のように突然の減給や倒産のリスクが低い点も大きなメリットです。特に、年功序列の昇給制度があるため、長く勤めるほど安定した収入を得られる傾向があります。
次に、ワークライフバランスの良さが人気の理由となっています。学校のスケジュールに沿って働くため、勤務時間が規則的で、繁忙期を除けば残業も少ない傾向があります。特に、夏休みや冬休みといった長期休暇中は業務量が減ることが多く、有給休暇も比較的取得しやすい環境です。これにより、家庭と仕事を両立しやすく、育児や介護といったライフイベントに柔軟に対応できる職場として評価されています。
また、職場環境が比較的落ち着いていることも勝ち組と言われる理由の一つです。一般企業のようにノルマや営業目標がないため、プレッシャーが少なく、精神的な負担が軽減されます。特に、事務職の仕事はルーティンワークが多いため、一度業務に慣れれば安定して働くことができます。これにより、「忙しすぎず、ほどよい働き方ができる職場」として認識されやすいのです。
さらに、福利厚生が充実している点も大きな魅力です。公務員としての待遇が適用されるため、住宅手当・扶養手当・通勤手当などの各種手当が整っており、退職金や年金制度も充実しています。また、産休・育休の取得実績も多く、女性にとっても働きやすい職場と言えるでしょう。
こうした理由から、学校事務は「勝ち組」と言われることが多く、特に公立学校の事務職は倍率が高くなる傾向にあります。ただし、すべての学校事務が楽な仕事とは限らず、職場環境や業務の忙しさには個人差があるため、事前にしっかりとリサーチすることが重要です。
やめとけと言われる理由と辞めたいと感じた時の選択肢

学校事務は「安定している」「働きやすい」といったイメージがある一方で、「やめとけ」と言われることもあります。その理由には、業務の負担や人間関係、キャリアの限界といった要素が関係しています。ここでは、学校事務の仕事を辞めたくなる理由と、辞めたいと感じた時に取るべき選択肢について解説します。
まず、「やめとけ」と言われる理由の一つとして業務の幅が広く、雑務が多いことが挙げられます。学校事務は、庶務・会計・人事・教務など幅広い業務を担当するため、一つの仕事に集中することが難しい環境です。特に、小規模な学校では一人で多くの業務をこなさなければならず、負担が大きくなりがちです。また、イベントの準備や突発的な対応が発生することも多く、「単なる事務職ではなく何でも屋のような立場になる」と感じる人もいます。
次に、人間関係のストレスが大きい点も辞めたくなる理由の一つです。学校事務は教員・保護者・業者など多くの人と関わるため、対人関係に悩むことが少なくありません。特に、教員との関係では、事務職員が軽視されることがあり、「学校運営の中で事務の重要性が理解されにくい」と感じることもあります。また、保護者からのクレーム対応や、生徒の問題に関わるケースもあり、精神的に疲れることがあるでしょう。
さらに、キャリアの限界を感じやすい点もデメリットとして挙げられます。公立学校の事務職は公務員であるため、異動はあっても基本的には昇進の機会が少なく、給与の上昇も緩やかです。そのため、長く働いてもキャリアアップのチャンスが少なく、「このままでいいのか?」と不安を感じる人もいます。特に、スキルを身につけても転職しにくいと感じることがあり、キャリアの将来性に悩むケースもあります。
こうした理由で「辞めたい」と感じた場合、いくつかの選択肢を検討することが大切です。まず、職場環境の改善を試みることが一つの方法です。人間関係の問題がある場合は、異動希望を出したり、上司に相談したりすることで解決できる可能性があります。また、業務負担が大きい場合は、業務の効率化を考えたり、他の職員と分担する方法を模索することも重要です。
次に、転職を視野に入れるという選択肢もあります。学校事務の経験を活かせる職種として、一般企業の経理・人事・総務職が挙げられます。特に、会計や給与計算の経験があれば、経理職への転職が比較的スムーズに進むことがあります。また、事務職の経験を活かして、行政書士や社会保険労務士といった資格を取得し、専門職としてキャリアチェンジする方法もあります。
さらに、「もう一度学校で働きたい」と考える場合、私立学校や大学の事務職に転職するのも一つの方法です。私立学校では、採用基準が公務員試験とは異なり、一般企業のような採用プロセスで職員を募集しているため、経験者が有利になることがあります。大学の事務職は給与水準が比較的高く、研究機関としての業務が多いため、学校事務の経験を活かしつつ新しい環境で働くことができます。
このように、学校事務を「やめたい」と感じた場合でも、改善できる方法や新たなキャリアの選択肢は存在します。まずは、自分が何に不満を感じているのかを明確にし、それを解決できる方法を考えることが重要です。転職を検討する場合でも、計画的に次のキャリアを考え、焦らず準備を進めることが成功の鍵となるでしょう。
学校事務の仕事はきつい?実態と魅力を総まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 学校事務の仕事は庶務・人事・会計・教務など多岐にわたる
- 公立学校の事務職は地方公務員であり、公務員試験の合格が必要
- 私立学校の事務職は民間企業の採用方式であり、公務員ではない
- 仕事内容はルーティン化しやすいが、繁忙期と閑散期の差が激しい
- 残業は比較的少ないが、学校行事などで休日出勤が発生することがある
- 保護者や地域住民の対応が大変で、クレーム処理の負担もある
- 教員との関係が難しく、学校によっては事務職員が軽視されることもある
- 有給休暇は取りやすいが、少人数の職場では調整が必要になる
- 給料は公務員としては安めだが、民間の事務職と比べると安定している
- 副業は禁止されており、収入を増やしたい場合の自由度が低い
- 「楽すぎ」と言われることがあるが、実際は業務の幅が広く負担も多い
- 異動が頻繁にあり、新しい職場環境に適応する必要がある
- 私立学校では給与水準や待遇にばらつきがあり、経営状態の影響を受ける
- 事務スキルやコミュニケーション能力が求められ、向き不向きが分かれる
- 転職先としては、一般企業の経理・総務、大学事務などの選択肢がある




