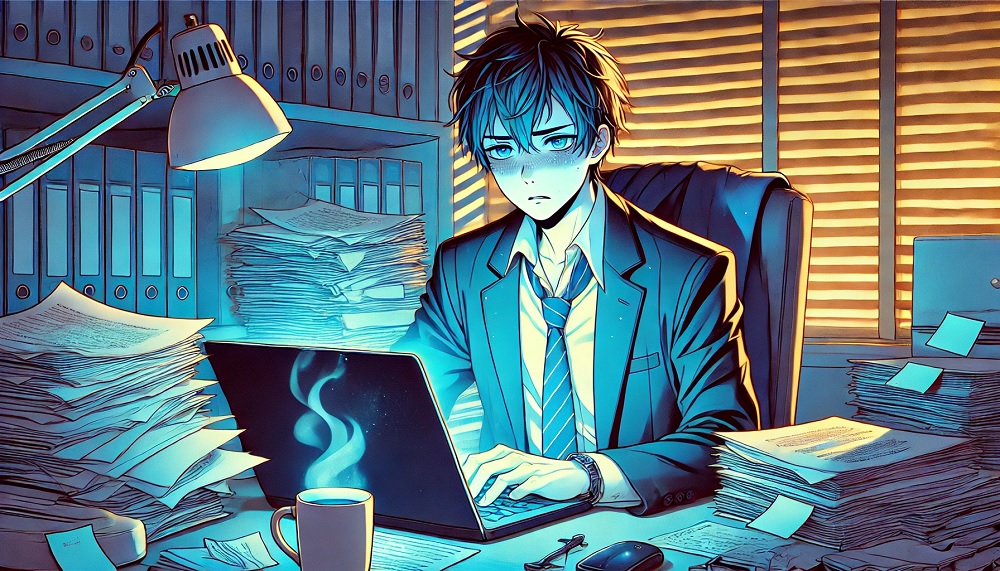外務省の仕事に興味があるものの、実際の働きやすさについて気になる人も多いのではないでしょうか。確かに、外交という特殊な業務を担う外務省は、忙しい日々が続くこともあり、激務と言われることが少なくありません。しかし、その一方で、やりがいが大きく、国際社会で活躍できる職場として人気の高い仕事でもあります。
本記事では、外務省の仕事内容や実際の勤務環境、外務省に向いている人の特徴などを詳しく解説します。楽しいと感じられる瞬間があるのか、それとも本当に過酷な環境なのか、実態を知りたい方に向けて、外務省の仕事のリアルをお届けします。
- 外務省の仕事がきついと言われる理由とその実態
- 仕事内容や業務の流れ、求められるスキル
- 外務省に入るにはどのような試験や学歴が必要か
- 年収やキャリアパス、海外勤務のメリットとデメリット
外務省の仕事はきつい?仕事内容と実態

- 仕事がきついと言われる理由
- 仕事内容は?何をするところ?
- 実は忙しい?残業時間の実態
- 英語レベルは?英語できないと無理?
- 外務省職員に向いている人の特徴
仕事がきついと言われる理由
外務省の仕事は、多くの人から「きつい」と言われることが少なくありません。その理由はいくつかありますが、主に業務の負担が大きいこと、国際情勢に左右される不規則な働き方、そして責任の重さが関係しています。
まず、外務省の仕事は非常に多岐にわたり、一つひとつの業務が専門性の高い内容となっています。外交政策の策定や国際会議の調整、各国との交渉、在外公館の運営、さらには邦人保護など、多方面にわたる仕事を同時並行でこなさなければなりません。このため、一つの仕事が終わっても次々と新しい案件が発生し、常に多忙な状態が続くのです。特に国際会議や要人訪問がある時期は、短期間で膨大な準備を行う必要があり、業務量が一気に増加します。
また、外務省の仕事は国際情勢の影響を強く受けます。例えば、国際的な紛争や災害が発生すれば、現地の邦人保護や緊急対応が求められます。このような状況では、昼夜を問わず対応する必要があり、長時間労働が避けられません。さらに、外交は相手国の都合に合わせて行われるため、時差の影響で深夜や早朝に業務が発生することもあります。
責任の重さも、仕事がきついと感じる大きな要因です。外交は国と国との関係を築く重要な業務であり、一つの判断ミスが国際問題に発展する可能性もあります。交渉や会議での発言一つひとつに慎重さが求められ、心理的なプレッシャーも大きいです。特に在外公館で働く場合は、現地の情勢に応じた対応が求められるため、柔軟かつ迅速な判断が不可欠となります。
これらの理由から、外務省の仕事は「きつい」と言われることが多いのです。しかし、その分やりがいも大きく、国際的な舞台で活躍したい人にとっては魅力的な職場でもあります。
仕事内容は?何をするところ?

外務省は、日本の外交を担う省庁であり、国内外で多岐にわたる業務を行っています。具体的には、外交政策の立案、国際交渉、在外公館の運営、邦人保護、文化交流などが含まれます。
まず、外務省の最も重要な役割は「外交政策の立案と実施」です。日本が国際社会の中でどのような立場を取るのかを決定し、各国との交渉を通じて日本の利益を守ることが求められます。例えば、自由貿易協定(FTA)の締結や安全保障政策の調整、気候変動問題に関する国際協力などが挙げられます。こうした政策を策定するために、国内外の情報を分析し、政府の方針を決定する業務が日常的に行われています。
また、「国際交渉」も外務省の重要な業務です。日本と他国との間で様々な課題について協議し、合意を取り付ける役割を果たします。G7やG20などの国際会議に参加し、日本の立場を主張することもあれば、二国間協議で経済や安全保障に関する合意を交わすこともあります。これらの交渉には高度な専門知識と交渉力が求められます。
「在外公館の運営」も外務省の仕事の一つです。世界各国にある日本大使館や領事館では、日本と相手国との関係を円滑にするための活動が行われています。外交官は現地政府との関係構築や情報収集を担当し、日本企業のサポートや文化交流活動なども行います。また、緊急時には邦人の安全確保や避難支援なども担います。
「邦人保護」も欠かせない業務です。海外で事件や事故が発生した際、日本人の安全を守るための対応を行います。特に、紛争地域や大規模災害が発生した場合には、迅速に情報を収集し、必要に応じて避難計画を立てることが求められます。
このほか、「文化交流活動」も重要な業務の一つです。例えば、日本文化を海外に紹介するためのイベントを開催したり、日本と他国の教育機関の交流を支援したりすることで、日本の国際的なイメージを向上させる役割を担います。
このように、外務省の仕事は多岐にわたります。国内で政策を立案する業務だけでなく、海外での交渉や文化交流の場でも活躍する機会があり、日本の国際的な立場を強化するために重要な役割を果たしているのです。
実は忙しい?残業時間の実態

外務省の仕事は「忙しい」と言われることが多く、その背景には複雑な業務内容や国際的なスケジュールが関係しています。一般的な省庁と比べても残業時間が長く、特に繁忙期には深夜まで業務が続くことも珍しくありません。
まず、外務省の残業時間が多い理由として、「国際情勢の変化に対応する必要がある」ことが挙げられます。外交は常に動いており、突然の国際問題や緊急事態に対応しなければならないことがあります。例えば、国際会議の準備や要人訪問の対応、災害や紛争への対応など、突発的な業務が発生するたびに残業が増える傾向があります。
また、「国際会議や交渉が夜間や早朝に行われることが多い」点も外務省の勤務環境を厳しくする要因です。外交交渉は相手国の都合に合わせる必要があり、時差の関係で日本時間の深夜や早朝に会議が設定されることもあります。そのため、勤務時間が不規則になりやすく、場合によっては長時間労働が続くこともあります。
特に本省勤務の場合、「繁忙期には連日深夜までの業務が続く」ことがあります。予算編成時期や国際会議の準備期間、国会対応などの重要な業務が重なると、残業が大幅に増加し、80時間を超えることもあると言われています。これに加えて、上司や関係各所との調整が必要な業務が多いため、業務の進行が遅くなり、さらに残業が増えることもあります。
一方で、海外勤務の場合は、「在勤手当が支給されるため、給与面では待遇が良い」ことが特徴です。海外赴任時には日本特有の残業文化が薄れる場合もありますが、現地の状況によっては休日出勤が求められることもあります。
このように、外務省の仕事は非常に多忙で、特に国内勤務では長時間労働が避けられないことが多いです。そのため、ワークライフバランスを重視する人にとっては厳しい職場である一方で、国際的な仕事に関わりたい人にとっては挑戦しがいのある環境と言えるでしょう。
英語レベルは?英語できないと無理?

外務省の仕事において英語は重要なスキルの一つですが、必ずしも英語が堪能でなければ採用されないわけではありません。しかし、業務の特性上、英語を使う場面は多く、一定以上の英語力が求められることは確かです。
外務省の職員は、日本政府の代表として国際的な場で活動するため、英語を含む外国語を使う機会が頻繁にあります。例えば、国際会議での通訳業務、各国政府との交渉、在外公館での情報収集、海外メディアとの対応などが挙げられます。これらの業務では、高度なリスニング力やスピーキング能力が求められる場面が多いため、英語を自在に操れると仕事の幅が広がります。
一方で、外務省の職員は必ずしも全員が最初から高度な英語力を持っているわけではありません。採用後には研修制度が整っており、特定の言語を習得するための「語学研修」も用意されています。この研修では、外務省が指定する研修語を2~3年かけて学び、現地での実践を通じて語学力を高めていきます。したがって、採用時点で英語が得意でなくても、意欲的に学ぶ姿勢があればスキルアップする機会が十分にあるのです。
ただし、外務省専門職員採用試験の受験を考えている場合、英語の試験があるため、最低限の英語力は必要になります。TOEFL iBT 100点以上またはIELTS 7.0以上が推奨されており、このスコアを目指すことで英語の基礎力を強化できます。また、外務省総合職の試験では、英語の他にフランス語、ドイツ語、中国語、ロシア語などの外国語を選択できるため、得意な言語があればそちらを活かすことも可能です。
英語が得意でなくても外務省に入ることはできますが、仕事をスムーズに進めるためには、ある程度の語学力が求められることは事実です。そのため、将来的に外務省で活躍したいと考えている人は、英語を中心に外国語の勉強を継続することをおすすめします。
外務省職員に向いている人の特徴
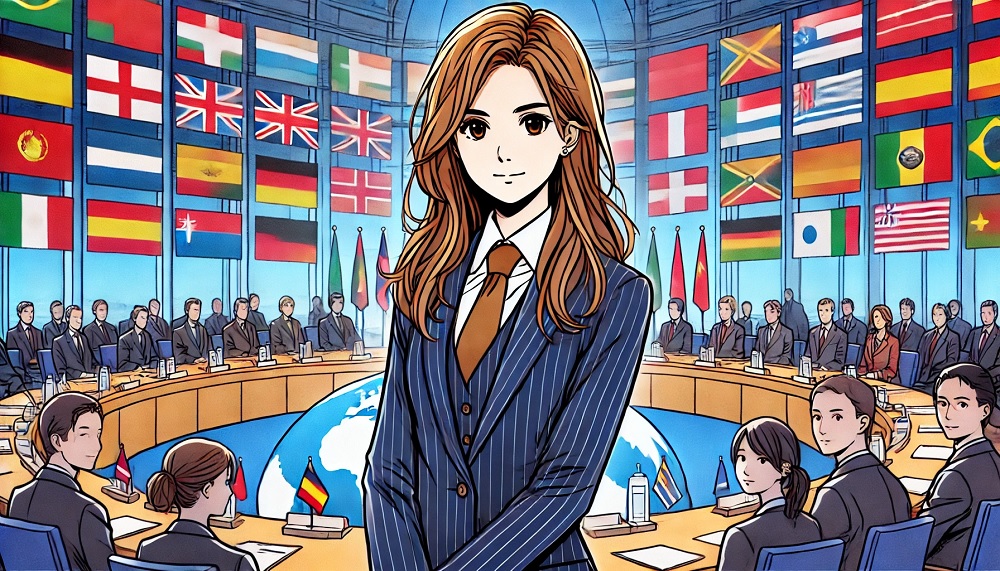
外務省の職員として活躍するためには、特定のスキルや性格が求められます。単に語学力があるだけではなく、外交官として国益を守り、国際社会の中で日本の立場を築くための資質が必要です。ここでは、外務省職員に向いている人の特徴について紹介します。
まず、最も重要なのは「柔軟な対応力と適応力」です。外務省の仕事は国内だけでなく、世界中の国々で行われます。そのため、異なる文化や価値観を持つ人々と接する機会が多く、その都度、適切な対応が求められます。特に在外公館に勤務する場合、現地の状況に合わせて臨機応変に対応する必要があるため、環境の変化に適応できる力が重要です。
次に、「コミュニケーション能力」も不可欠です。外交官は各国の政府関係者、企業、国際機関の担当者などと関わりながら、日本の立場を伝え、交渉を進める役割を担います。そのため、相手の意図を正しく理解し、適切に意見を伝える能力が求められます。また、単に話が上手いだけではなく、相手の文化や慣習を尊重しながら対話を進めるスキルが必要です。
さらに、「高い責任感と忍耐力」も欠かせません。外務省の仕事は、国際問題や国家間の交渉など、非常に重要な案件を扱います。そのため、一つひとつの業務に対して強い責任感を持ち、慎重に対応する姿勢が求められます。また、外交交渉は一朝一夕で成果が出るものではなく、長期間にわたる調整が必要なことが多いため、忍耐強く取り組める人に向いています。
加えて、「ストレス耐性と精神的なタフさ」も重要な要素です。外務省の仕事は激務になることが多く、特に本省勤務では連日長時間労働が続くこともあります。また、国際情勢の変化によって突発的な対応が求められることもあり、精神的なプレッシャーが大きくなる場面も少なくありません。そのため、ストレスに強く、プレッシャーの中でも冷静に業務を遂行できる人が求められます。
最後に、「チームワークを大切にできる人」も外務省で活躍しやすいでしょう。外交は個人プレーではなく、チームでの連携が不可欠です。政策の立案や交渉の準備、在外公館の運営など、あらゆる業務において職員同士の協力が求められます。そのため、自分の意見を主張しつつも、他者と円滑に連携できる協調性が必要になります。
このように、外務省職員には語学力だけでなく、柔軟な対応力、コミュニケーション能力、責任感、ストレス耐性、チームワークなど、多くの資質が求められます。これらの特徴を持つ人は、外務省での仕事に適性があると言えるでしょう。もし外務省で働くことを考えているのであれば、これらのスキルを意識的に磨くことが重要です。
外務省の仕事はきついが人気?評判と年収
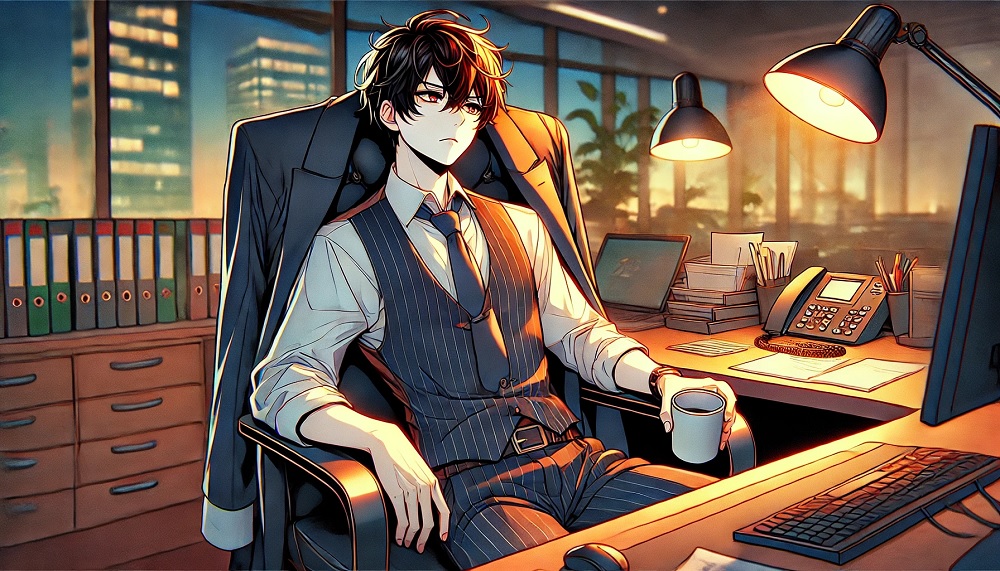
- 外務省に入るには?必要な学歴や出身大学
- 難易度は?試験の合格率と対策
- 職員の年収はどのくらい?
- 人気の理由とは?
- 仕事は楽しい?やりがいと魅力
外務省に入るには?必要な学歴や出身大学
外務省に入るためには、主に「国家総合職試験」または「外務省専門職員採用試験」に合格する必要があります。それぞれの試験には受験資格や求められる能力に違いがあり、自分のキャリアプランに合わせて選択することが重要です。
国家総合職試験を受験する場合、学歴の要件は特に定められていませんが、実際には大学卒業者がほとんどです。特に、東京大学、京都大学、一橋大学、早稲田大学、慶應義塾大学などの上位大学の出身者が多く、これらの大学からは毎年複数名の合格者が出ています。これは、総合職試験が非常に難易度の高い試験であるため、高い学力が求められることが理由の一つと考えられます。また、外交官としてのキャリアを目指す学生は、大学在学中から専門知識を深め、民間の予備校や対策講座を活用して勉強することが一般的です。
一方、外務省専門職員採用試験は、特定の地域や言語に精通した人材を求める試験であり、外国語や国際関係の学問を専攻している人が多く受験します。このため、東京外国語大学、大阪大学、上智大学などの国際系学部を持つ大学の出身者が目立ちます。ただし、この試験では専門的な知識と語学力が重視されるため、必ずしも有名大学の出身である必要はなく、海外大学出身者も合格しているケースがあります。
学歴だけでなく、外務省に入るためには幅広い知識と柔軟な思考力が求められます。特に、語学力、国際政治や経済の知識、論理的な思考力が重要視されるため、大学在学中からしっかりと対策を進めることが大切です。また、面接試験では人物評価も重視されるため、志望動機や外交官としての適性をしっかりとアピールできる準備をしておくことが求められます。
難易度は?試験の合格率と対策

外務省の採用試験は非常に難易度が高く、毎年多くの受験者が挑戦するものの、最終合格者はごく一部に限られます。特に、国家総合職試験(外務省志望)と外務省専門職員採用試験は、それぞれ異なる特徴を持ち、合格するためには徹底した準備が必要です。
国家総合職試験は、日本全国の中央省庁で幹部候補を採用するための試験であり、外務省だけでなく他の省庁も対象となります。この試験の倍率は非常に高く、毎年数千人が受験する中で、外務省に採用されるのは30~40名程度です。一次試験では「基礎能力試験」「専門試験」「政策論文」などが課され、高度な知識が必要とされます。さらに、二次試験では個別面接やグループ討論が行われ、外交官としての適性が評価されます。
外務省専門職員採用試験は、特定の地域や言語に特化した専門職員を採用する試験であり、一般的に倍率は5~15倍程度とされています。この試験では、憲法・国際法・経済学などの専門知識に加え、外国語試験が課されます。特に、英語以外の言語(中国語、ロシア語、フランス語など)を選択する場合は、より高度な語学力が求められることが特徴です。また、二次試験では面接や外国語会話試験が行われ、受験者の適性が総合的に判断されます。
これらの試験に合格するためには、大学在学中からしっかりとした対策が必要です。予備校の講座を活用する、過去問を徹底的に解く、模擬面接で実践的な準備をするなど、計画的に取り組むことが重要です。また、語学力の向上も欠かせないため、日常的に英語や他の外国語に触れる機会を増やし、実践的なスキルを身につけることが合格への近道となります。
職員の年収はどのくらい?
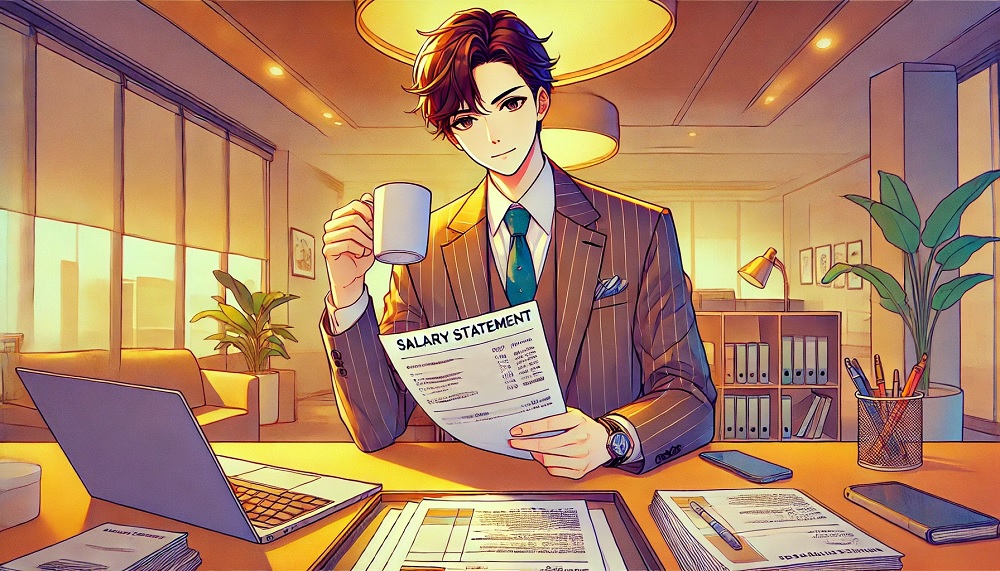
外務省の職員の年収は、役職や経験年数、勤務地(国内・海外)によって大きく異なります。一般的には、他の省庁の国家公務員と比較して給与水準は高めですが、その分業務の負担も大きいことが特徴です。
まず、新卒の初任給は、国家総合職の場合、大学院卒で約26.4万円、大卒で約23.2万円となっています。外務省専門職の場合は、大卒で約22.5万円です。これに加えて、年2回の賞与(ボーナス)が支給され、初年度の年収は約350~400万円程度となります。
年齢とともに昇給し、30代で係長級の書記官に昇進すると、年収は約750万円程度になります。特に、海外勤務となると、日本国内の給与に加えて「在勤手当」が支給されるため、年収が大きく増加します。在勤手当の金額は勤務地によって異なりますが、例えばアメリカでは月額約47万円、アフリカの一部の国では約66万円が支給されるケースもあります。このため、海外勤務の期間中は年収が1000万円を超えることも珍しくありません。
さらに、40代で課長補佐級になると年収は約1000万円前後、50代で課長や参事官クラスに昇進すると、1200~1300万円程度になります。局長クラスになると、年収は約1700万円を超えることもあります。
| 年齢(目安) | 役職 | 年収(目安) |
|---|---|---|
| 25歳 | 一般職員(新人) | 約315万円 |
| 30歳 | 係長級(書記官) | 約750万円 |
| 40歳 | 課長補佐級 | 約1,000万円 |
| 50歳 | 本府省課長・参事官 | 約1,200~1,300万円 |
| 50歳以上 | 局長クラス | 約1,700万円以上 |
また、外務省の給与にはさまざまな手当が含まれています。国内勤務では扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当などが支給され、特に残業が多い時期には超過勤務手当が大きな割合を占めることもあります。海外勤務では、在勤手当のほか、住居費や医療費の補助などが支給され、生活環境によっては非常に手厚い待遇が用意されています。
ただし、給与が高い一方で、長時間労働や海外勤務の負担が大きいことも事実です。特に、海外勤務では生活環境が大きく変わるため、適応力が求められます。国内勤務でも、繁忙期には残業が続くことがあり、ワークライフバランスを確保するのが難しい面もあります。
このように、外務省の職員の年収は比較的高水準ですが、その分業務の責任や負担も大きくなるため、自分に合った働き方ができるかを考えることが重要です。
人気の理由とは?

外務省の仕事は、国家公務員の中でも特に人気が高い職種の一つです。その理由として、国際的な舞台で活躍できる点、高い給与水準、充実したキャリアパスなどが挙げられます。
まず、多くの人が外務省を志望する理由の一つに「国際的な仕事ができる」という点があります。外交官や専門職員として、日本を代表して海外の政府関係者や国際機関と交渉を行う機会が多く、グローバルな視点で仕事を進められることが魅力です。また、在外公館勤務では実際に海外で働くことになり、異文化の中での仕事や生活を経験できるのも特徴の一つです。世界各国での勤務経験を積むことで、広い視野を持ち、日本の国際関係に直接貢献できる点は、多くの志望者にとって大きな魅力となっています。
次に、「給与や待遇が良い」ことも人気の理由です。国家公務員の中でも、外務省職員は比較的高い給与を得ることができます。特に、海外勤務の場合は「在勤手当」が加算され、勤務地によっては年収1000万円を超えることもあります。さらに、住宅手当や扶養手当などの福利厚生も充実しており、安定した収入を得ながらキャリアを築ける環境が整っています。
また、「キャリアパスの多様性」も外務省が人気の理由の一つです。総合職として入省した場合、将来的には大使や国際機関の幹部として活躍する可能性があります。専門職員の場合も、特定の国や地域に関する専門知識を深め、エキスパートとしてキャリアを築くことができます。さらに、外務省で培った知識や経験は、民間企業や国際機関への転職にも活かせるため、長期的なキャリア形成においても有利です。
加えて、「社会的意義のある仕事ができる」ことも外務省の人気を支える要因です。外交は国益を守るための重要な業務であり、国際問題の解決や日本の立場を強化する役割を担っています。そのため、自分の仕事が日本や国際社会に直接影響を与えるという実感を得ることができ、やりがいを感じる人が多いのも特徴です。
このように、外務省の仕事は、国際的な舞台で活躍できる点、高い給与や待遇、充実したキャリアパス、社会的意義のある仕事ができる点など、多くの魅力があるため、多くの志望者が集まる職種となっています。
仕事は楽しい?やりがいと魅力

外務省の仕事は、多くの人にとって非常にやりがいのある職業ですが、一方で大変な部分も多いのが実情です。しかし、その厳しさを上回る魅力があるため、長年にわたって働き続ける職員が多いのも特徴です。
まず、「国際的な業務に携われること」は、外務省の仕事の大きな魅力の一つです。外交官として各国の政府関係者と交渉を行ったり、日本を代表して国際会議に参加したりする機会があり、グローバルな視点で仕事ができる点が大きなやりがいにつながります。例えば、自由貿易協定(FTA)や環境問題に関する交渉に携わり、日本の立場を国際的に強化する役割を果たすことができます。
また、「多くの人と関わる機会があること」も、外務省の仕事の面白さの一つです。政府関係者だけでなく、国際機関、民間企業、学術機関など、さまざまな分野の専門家と協力しながら業務を進めるため、多くの知見を得ることができます。さらに、在外公館勤務では、現地の文化や社会を深く知ることができるため、異文化理解を深めながら仕事をすることができます。
「成果が目に見えること」も、外務省の仕事の大きなやりがいの一つです。外交交渉は長期間にわたることが多いですが、合意が成立したときや、日本の立場が国際的に認められたときには大きな達成感を得ることができます。また、国際会議の成功や日本企業の海外進出支援、邦人保護活動など、自分の仕事が具体的な成果として表れることが多いため、モチベーションを維持しやすいのも特徴です。
一方で、「ハードワークであること」も事実です。特に本省勤務では、連日深夜までの業務が続くこともあり、ワークライフバランスを確保するのが難しい場合もあります。また、国際情勢に左右されるため、急な出張や休日出勤が発生することも珍しくありません。そのため、外務省で働くには、ストレス耐性や柔軟な対応力が求められます。
しかし、このような厳しい環境の中でも、外交官としての役割を果たし、日本の国益を守ることに貢献できるという点で、大きなやりがいを感じる人が多いのも事実です。さらに、外務省でのキャリアを通じて培ったスキルは、国際機関や民間企業など、さまざまな分野で活かすことができるため、将来的なキャリアの選択肢が広がる点も魅力の一つです。
このように、外務省の仕事は大変な部分も多いですが、それを上回るやりがいと魅力があるため、多くの職員が誇りを持って働いています。国際的な業務に関心があり、日本の外交を支えたいと考えている人にとっては、非常にやりがいのある仕事と言えるでしょう。
外務省の仕事はきつい?実態と特徴を総括
この記事のポイントをまとめます。
- 外務省の仕事は業務量が多く、常に多忙な状態が続く
- 国際情勢の影響を受け、突発的な業務が発生しやすい
- 時差の関係で深夜や早朝に業務が発生することがある
- 一つの判断ミスが国際問題に発展する可能性がある
- 外交政策の立案、国際交渉、邦人保護など業務が多岐にわたる
- 在外公館勤務では現地政府との交渉や文化交流を行う
- 外務省の残業時間は長く、繁忙期には80時間を超えることもある
- 海外勤務では在勤手当が支給され、給与水準が高くなる
- 英語は必須ではないが、業務を円滑に進めるには必要なスキル
- 採用試験の難易度が高く、合格率は低い
- 外務省職員には柔軟な対応力と高いストレス耐性が求められる
- キャリアパスが多様で、大使や国際機関の幹部への道もある
- 社会的意義のある仕事であり、日本の国益に貢献できる
- 国際的な舞台で活躍できるため、やりがいが大きい
- 長時間労働が伴うものの、グローバルな視点を持てる職場