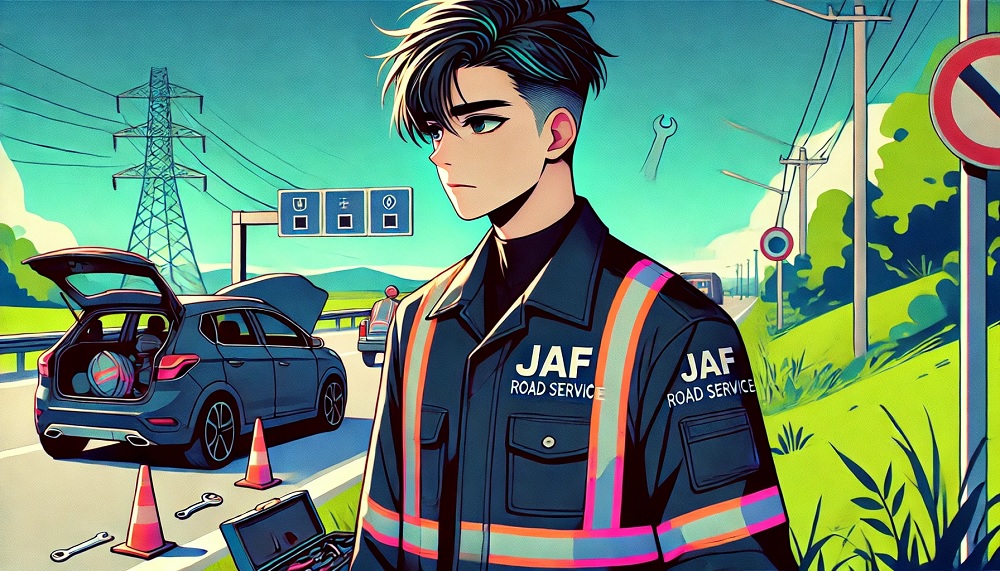学校用務員の仕事に興味があるものの、「用務員の仕事はきついのでは?」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。実際に働いている人の中には、業務の負担が大きく辞めたいと考えるケースもありますが、一方でやりがいを持って楽しいと感じながら働く人もいます。
本記事では、用務員の仕事内容を詳しく解説し、どのような人が向いてる人なのかを考えながら、現場の実態を紹介していきます。特に、女性が働きやすい職場なのか、若い人が少ない理由、給料の相場など、気になるポイントを網羅しています。また、用務員になるにはどのような方法があるのか、公立・私立の違いや採用試験の有無についても詳しく説明します。
「用務員の仕事はどんなものか知りたい」「働き続けるべきか悩んでいる」「転職を考えている」といった方に向けて、実態を詳しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。
- 用務員の仕事内容と業務の負担の実態
- 仕事がきついと感じる理由と辞めたい人の本音
- 女性や若い人が少ない理由と働きやすさ
- 給料相場や用務員になるにはどうすればいいか
用務員の仕事はきつい?仕事内容と実態

- 仕事内容は?業務内容を解説
- 用務員の一日の流れを詳しく紹介
- 向いてる人の特徴とは?
- 女性でもできる?
- 給料・年収はどのくらい?
仕事内容は?業務内容を解説
用務員の仕事は、学校の環境維持や施設管理を中心に、多岐にわたる業務を担当します。主な業務内容は、校舎や校庭の清掃、設備の点検や修繕、備品の管理、学校行事の準備などです。業務内容は自治体や学校によって異なりますが、大まかな流れは共通しています。
まず、校舎や校庭の清掃は、用務員の重要な役割の一つです。廊下や階段、教室、トイレなどの清掃を行い、常に衛生的な環境を保つことが求められます。特にトイレの清掃は毎日欠かせず、衛生管理の観点からも丁寧に行う必要があります。また、校庭の落ち葉掃除や除草作業も、学校の美観を維持するための重要な仕事です。
次に、設備の点検や修繕です。学校にはさまざまな設備や備品がありますが、長期間使用していると不具合が発生することがあります。例えば、電球の交換、ドアの修理、蛇口の水漏れ対応など、簡単な修繕作業は用務員が対応します。高度な修理が必要な場合は、専門業者へ依頼することになりますが、日常的なメンテナンスを行うことで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。
また、備品の管理や手配も重要な業務の一つです。学校では、机や椅子、掃除用具、文房具などさまざまな備品が必要になります。壊れたり不足したりした場合、適切に補充や修理を行うのも用務員の仕事です。特に、年度の変わり目には新しい備品の手配や古い備品の処分などが発生し、多忙になることが多いです。
さらに、学校行事の準備や補助も用務員の役割です。入学式や卒業式、運動会、文化祭など、さまざまな行事の準備をサポートします。例えば、会場の設営、備品の運搬、テントの設置など、事前の準備だけでなく、当日の運営補助も求められることがあります。行事が円滑に進むよう、裏方として支えるのが用務員の大切な役割です。
このように、用務員の仕事は多岐にわたり、学校の環境維持に欠かせない存在です。一見地味な仕事に見えるかもしれませんが、学校全体の運営を支える重要な役割を担っているといえるでしょう。
用務員の一日の流れを詳しく紹介
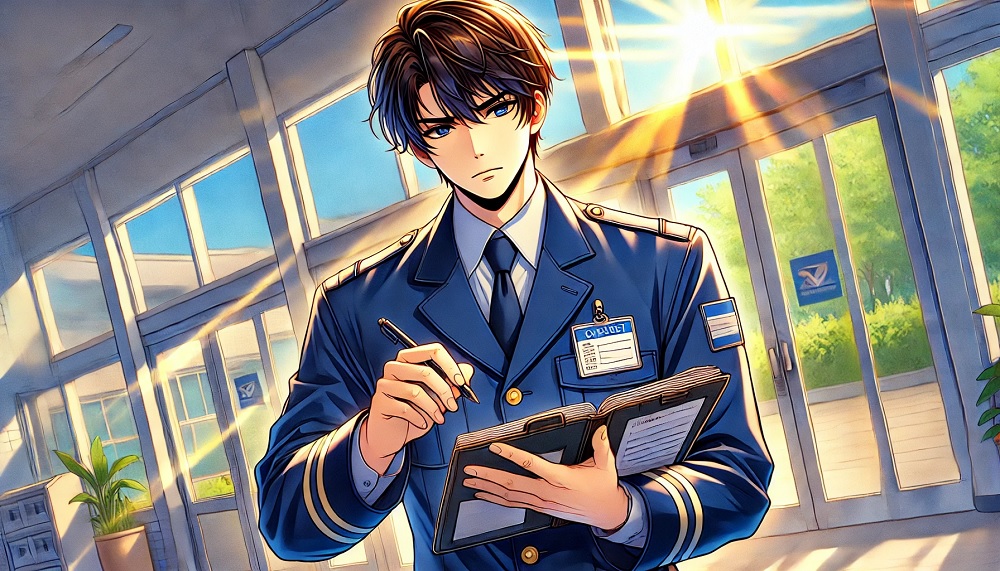
用務員の一日は、朝早くから始まります。以下は一例として参考にしてください。
出勤後、まずは校舎や校庭の点検を行い、異常がないかを確認することから始まります。特に、校門の開錠や警備システムの解除、照明の点灯確認などを行い、児童・生徒や教職員が安全に過ごせる環境を整えることが重要です。
午前の業務では、校舎内の清掃が中心になります。トイレや廊下、教室の掃除を行い、衛生的な環境を維持します。特にトイレの清掃は毎日行い、衛生管理を徹底する必要があります。また、昇降口の掃除やスリッパの整理も行い、訪問者や児童・生徒が気持ちよく学校生活を送れるようにします。さらに、校庭の巡回や除草作業を行い、学校全体の美観を維持します。
昼休みの時間帯は、職員室や特別教室のゴミ回収を行ったり、備品の補充や管理を行ったりします。また、急な修理依頼があれば対応することもあります。例えば、机や椅子の故障、ドアの不具合、電球の交換など、小さな修繕作業が発生することも少なくありません。
午後の業務では、主に設備の点検や修繕作業を行います。校舎や体育館の設備、屋上や給水設備など、普段見えにくい場所の点検を実施します。また、学校行事の準備がある場合は、会場の設営や必要な備品の運搬などを行います。特に、大きな行事の前は準備作業が多くなり、スケジュールに追われることもあります。
放課後の業務としては、最終的な点検と片付けが中心です。校内の巡回を行い、異常がないか確認します。特に、生徒が帰った後のトイレや教室の点検、施錠作業をしっかり行うことが求められます。また、ゴミの分別や回収を行い、清潔な状態を保つことも重要です。
このように、用務員の仕事はルーチンワークが多いですが、その日の状況によって対応する業務が変わることもあります。設備の故障や修理依頼、急な行事準備など、臨機応変な対応が求められる場面も多いでしょう。
向いてる人の特徴とは?

用務員の仕事は、清掃や設備管理などの裏方業務が中心ですが、学校の円滑な運営に欠かせない重要な役割を担っています。そのため、向いている人にはいくつかの特徴があります。
まず、細かいことに気がつく人は、用務員に向いています。学校の設備や環境を維持するためには、小さな異常に気づき、早めに対応することが求められます。例えば、「壁にひびが入っている」「トイレの水が流れにくい」「電球が切れそう」など、小さな変化に敏感であることが大切です。
次に、コツコツと作業を続けられる人も向いています。清掃や修繕作業は、毎日決まったルーチンワークが多く、地道な作業が中心になります。単調な作業が苦にならず、粘り強く続けられる人に適した仕事といえるでしょう。
また、体を動かすことが好きな人も、用務員の仕事に向いています。屋内外の清掃や修繕作業、荷物の運搬など、一定の体力が求められます。特に夏場の草刈り作業や、冬場の除雪作業など、季節ごとに負担のかかる作業もあるため、体力に自信がある人の方が働きやすいでしょう。
さらに、周囲と円滑にコミュニケーションが取れる人も重要です。用務員は、教職員や生徒、業者など、さまざまな人と関わる機会があります。特に、学校行事の準備や修繕作業では、他の職員と協力しながら進めることが多いため、スムーズに意思疎通ができる人が向いています。
このように、用務員に向いている人は、細やかな気配りができ、コツコツと作業をこなし、一定の体力とコミュニケーション能力を備えている人といえます。反対に、ルーチンワークが苦手な人や、体を動かすのが嫌いな人には、あまり向いていないかもしれません。
女性でもできる?

用務員の仕事は、清掃や設備の点検、修繕、学校行事の準備など幅広い業務を担当しますが、女性でも十分に務まる仕事です。実際に、女性の用務員として働いている人も少なくありません。ただし、一部の業務には体力を要するものがあるため、その点を理解した上で検討することが重要です。
女性が活躍しやすい業務としては、室内清掃や備品管理、来客対応、植物の手入れなどがあります。特に清掃業務は、日常的に行う作業のため、学校の衛生環境を維持する重要な役割を担います。また、備品管理では、文房具や消耗品の補充、整理整頓などの業務が含まれます。こうした業務は力仕事が少なく、女性でも無理なくこなせるでしょう。
一方で、体力が求められる業務も存在します。例えば、机や椅子の移動、校庭の草刈り、大型備品の修理などは、ある程度の力が必要です。ただし、こうした業務も全てを一人で行うわけではなく、他の用務員や教職員と協力して進めることができます。そのため、女性だからといって難しいわけではありません。また、自治体や学校によっては、負担の大きい作業は外部業者に依頼するケースも増えているため、業務内容が軽減されることもあります。
さらに、女性ならではの気配りが活かせる場面も多いです。例えば、学校には小さな子どもが多いため、細かな気配りや優しい対応が求められる場面があります。子どもたちが安心して過ごせるよう、細かい清掃や整備を意識することで、より快適な学校環境を作ることができるでしょう。また、行事の際の飾り付けや準備など、細やかな作業が得意な人には向いている業務も多くあります。
結論として、用務員の仕事は女性でも問題なくこなせる業務が多く、実際に活躍している人もいます。力仕事が苦手な場合でも、工夫次第で対応できるため、大きなハードルにはなりません。むしろ、細やかな気配りや丁寧な作業が求められる場面では、女性の強みが発揮できる仕事といえるでしょう。
給料・年収はどのくらい?
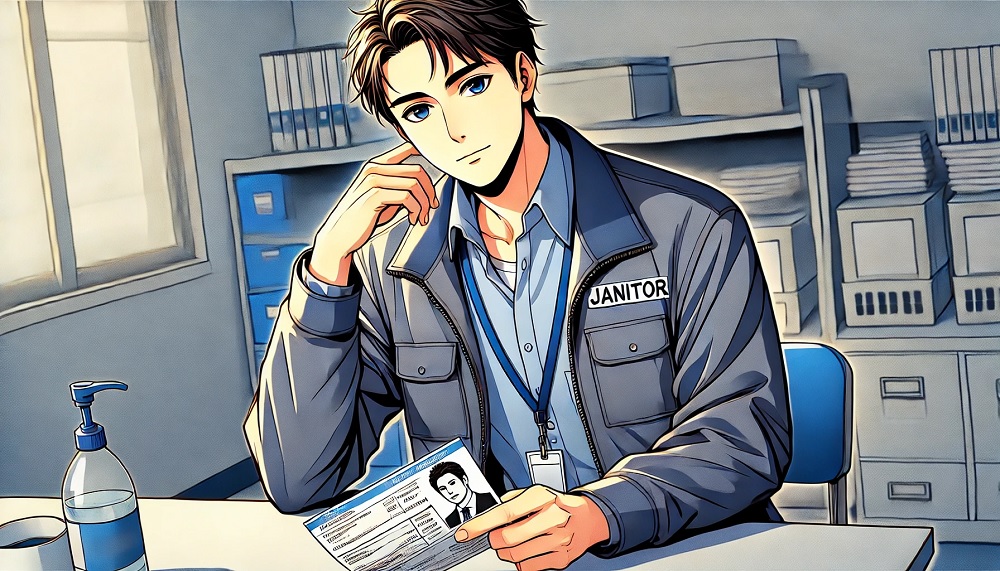
用務員の給料や年収は、勤務先や雇用形態によって大きく異なります。公立学校の用務員は基本的に公務員の扱いとなるため、安定した給与体系が確立されています。一方、私立学校や派遣社員として働く場合は、契約内容によって給与に差が生じることが一般的です。
まず、公立学校の正規職員としての用務員の場合、給与は地方公務員の給与規定に基づき支給されます。初任給は地域によって異なりますが、月給はおおよそ18万~22万円程度が一般的です。さらに、年2回のボーナス(賞与)が支給され、年間の合計額は4~5カ月分になることが多いです。そのため、年収にすると350万~450万円程度が相場となります。また、勤続年数に応じて昇給があり、長く働くほど給与は安定して増えていきます。さらに、福利厚生や退職金制度も整っているため、安定した職業として人気があります。
一方、私立学校の契約社員やパート・アルバイトとして働く用務員の場合、給与水準は公立学校よりも低めになる傾向があります。特にパート・アルバイトの場合、時給制で雇用されることが多く、時給1,000~1,300円程度が一般的です。フルタイムで働いた場合の月収は約15万~18万円程度となり、年収は200万円~300万円ほどになります。私立学校の契約社員であれば、もう少し給与水準が高くなることもありますが、公務員と比べると不安定な要素も多くなります。
また、派遣社員としての用務員の場合、給与は契約内容によって変動します。派遣会社を通じて働くため、学校との直接雇用ではなく、仕事内容も限定されることが多いです。一般的な時給は1,200円~1,500円程度で、フルタイム勤務の場合の年収は250万~350万円程度になります。ただし、派遣の場合は雇用の継続が保証されていないため、契約更新の有無によって収入が不安定になるリスクがあります。
このように、用務員の給与は雇用形態や勤務先によって大きく異なります。公立学校の正規職員であれば安定した収入を得られる一方、私立や派遣の場合は給与が低めで、雇用の安定性にも注意が必要です。そのため、長期的に安定した収入を希望する場合は、公立学校の正規職員としての採用試験を受けることが有利でしょう。
用務員の仕事はきつい?辞めたいと感じる理由
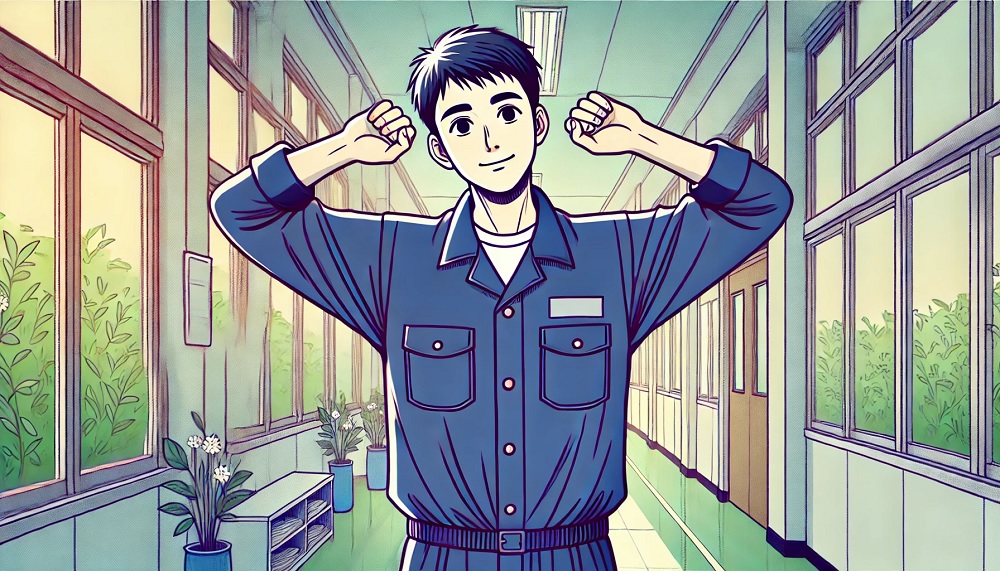
- 仕事しない?楽と言われる理由と実態
- 楽しい?やりがいを感じるポイント
- 若い人がいない?20代が少ない理由
- 用務員になるには?必要な条件と採用方法
- 仕事を続けるか?辞めたい人の選択肢
仕事しない?楽と言われる理由と実態
用務員の仕事は「楽そう」「あまり仕事をしていないのでは?」といったイメージを持たれがちですが、実際の業務内容を見ると、その認識は必ずしも正しくありません。学校の維持管理という裏方の仕事が多いため、目立たないだけであり、決して仕事が少ないわけではないのです。
「楽そう」と言われる理由の一つは、勤務時間が比較的安定していることです。
公立学校の用務員の場合、基本的に朝から夕方までの勤務が一般的であり、夜遅くまでの残業が発生することはほとんどありません。また、夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中は、生徒がいないため比較的業務量が減ることが多く、こうした点が「楽な仕事」というイメージにつながっていると考えられます。
また、「単調な作業が多い」ことも、楽に見える要因の一つです。
用務員の仕事は、清掃や備品の整理、設備の点検、修繕などのルーチン業務が中心となるため、一度仕事に慣れてしまえば流れがつかみやすいのが特徴です。特に、日々の清掃や点検作業は決まったスケジュールで行われるため、突発的な業務が少ないと感じる人もいるでしょう。
しかし、実際には用務員の仕事には臨機応変な対応が求められる場面が多いことも事実です。例えば、突発的な修繕作業が発生した場合にはすぐに対応しなければならず、学校行事の準備や後片付けでは多くの力仕事をこなす必要があります。特に体育祭や文化祭、入学式・卒業式などの行事前後は、通常業務に加えて多くの雑務が発生するため、決して「楽」とは言い切れません。
さらに、学校の安全管理も重要な業務の一つです。校舎や設備の点検を怠ると事故につながる可能性があるため、常に注意を払いながら仕事をする必要があります。また、学校内で発生したトラブルや設備の故障にも迅速に対応しなければならず、責任のある仕事といえるでしょう。
こうした実態を考えると、用務員の仕事は決して「楽」ではなく、むしろ日々の業務を着実にこなしていく忍耐力や、トラブルに即座に対応できる柔軟性が求められる仕事であることがわかります。
楽しい?やりがいを感じるポイント

用務員の仕事は、単調に見える業務が多いものの、やりがいを感じられるポイントも多くあります。学校の環境を整え、子どもたちが快適に過ごせる場を作ることに貢献できるため、達成感を得られる場面も少なくありません。
最も大きなやりがいは、「学校環境を支えている実感を持てること」です。
清掃や修繕作業、備品の管理など、用務員の仕事は目立たないことが多いですが、これらが適切に行われていることで学校全体が円滑に運営されます。例えば、教室やトイレが清潔に保たれていることで、子どもたちが快適に学習できる環境が整い、壊れた備品を修理することで、安全に学校生活を送ることができます。こうした「自分の仕事が学校全体の快適さに直結している」という実感を持つことができる点は、大きなやりがいの一つです。
また、「生徒や教職員からの感謝の言葉」も、仕事の励みになります。
用務員は直接授業をするわけではありませんが、子どもたちと日常的に接する機会があります。掃除をしている際に「いつもありがとうございます」と声をかけられたり、修繕作業を終えた後に先生から「助かりました」と感謝されたりすることで、自分の仕事が役に立っていると実感できるでしょう。こうした人とのふれあいが、仕事のモチベーションにつながることもあります。
さらに、「自分の手で環境を整える達成感」も魅力の一つです。
例えば、放置されていた草木を剪定して校庭をきれいにしたり、壊れていた設備を修理して使えるようにしたりすることで、目に見える成果が得られます。自分が手を加えたことで環境が改善され、それを子どもたちや先生が喜んでくれると、大きな満足感を得られるでしょう。
このように、用務員の仕事は、単調に思える部分もありますが、その中にも多くのやりがいを見出すことができます。学校という場を支える仕事として、誇りを持って働ける点が大きな魅力といえるでしょう。
若い人がいない?20代が少ない理由

学校の用務員には、50代以上の職員が多く、20代の若い人が少ないのが現状です。その理由はいくつか考えられますが、主に「採用の仕組み」「給与の水準」「仕事内容のイメージ」が関係しています。
第一に、採用の仕組みが20代の就職には向いていないことが挙げられます。
公立学校の用務員は、多くの場合、自治体が実施する採用試験を受けて合格する必要があります。しかし、用務員の募集は頻繁に行われるものではなく、新規採用の枠が少ないことが一般的です。また、多くの自治体では即戦力として経験者を優先する傾向があるため、20代の若年層が応募しにくい状況が続いています。
次に、給与水準が20代の就職希望者にとって魅力的でないことも理由の一つです。
公務員として採用された場合、安定した収入を得られるものの、初任給はそれほど高くなく、昇給スピードもゆるやかです。また、私立学校や派遣として働く場合は、さらに給与が低くなることが多く、20代の若い世代が積極的に選ぶ職業とはいえません。特に、より高収入を求める人にとっては、用務員の仕事は魅力が少ないと感じられるでしょう。
さらに、仕事内容のイメージも若い人が少ない要因となっています。
用務員の仕事は「裏方」「雑用」と見られがちで、キャリアアップの機会が少ないため、若い世代が長期的なキャリアとして選びにくいという側面があります。また、現場作業が中心であり、事務職のようにデスクワークがメインではないため、体力的な負担を考えて敬遠する人もいます。
このように、20代の若い人が少ないのは、採用枠の少なさや給与面の問題、仕事のイメージなど、複数の要因が絡んでいるためです。しかし、学校運営に欠かせない重要な仕事であり、長期的に安定して働ける点では、魅力のある職業の一つともいえるでしょう。
用務員になるには?必要な条件と採用方法

用務員になるためには、どの学校で働くかによって採用の方法が異なります。公立学校で働く場合、多くの自治体では地方公務員として採用されるため、自治体が実施する技能労務職員の採用試験を受ける必要があります。一方、私立学校では各学校が独自に求人を出しており、一般企業と同じように書類選考や面接を経て採用されることが一般的です。また、最近では派遣会社やビルメンテナンス会社を通じて学校に派遣される形で働くケースも増えています。それぞれの雇用形態には特徴があり、自分の働き方に合った方法を選ぶことが大切です。
公立学校の用務員になるためには、まず自治体ごとの募集要項を確認し、採用試験に申し込む必要があります。試験の内容は自治体によって異なりますが、一般的には筆記試験と面接試験が課されます。筆記試験は一般常識や適性検査が中心で、公務員試験のように高度な学力が必要とされるわけではありません。ただし、自治体によっては応募者が多く倍率が高くなることもあるため、しっかりと試験対策を行うことが重要です。また、公立学校の用務員として採用されると、自治体内の複数の学校を異動しながら働くことが一般的です。勤務地を選ぶことは難しく、数年ごとに異動があることを理解しておく必要があります。しかし、地方公務員として雇用されるため、給与や福利厚生が安定しており、長期的に安心して働ける環境が整っています。
私立学校で用務員になる場合は、各学校が独自に求人を出しているため、希望する学校の採用情報をチェックし、応募することになります。私立学校では公立学校のような統一された試験はなく、書類選考や面接による採用が一般的です。公立学校と違い、異動の可能性がほぼなく、採用された学校で長く勤務できるのが特徴です。ただし、正規職員としての募集が少なく、契約社員やアルバイトとしての雇用が多いため、安定した収入を求める場合は注意が必要です。給与水準も公立学校に比べると低めになることが多く、雇用形態や待遇をよく確認したうえで応募することが大切です。
近年では、一部の自治体や学校で用務員業務を民間のビルメンテナンス会社や派遣会社に委託するケースも増えています。この場合、学校に直接雇用されるのではなく、派遣会社を通じて勤務する形になります。派遣の用務員は契約期間が決まっていることが多く、契約が更新されない可能性がある点には注意が必要です。また、公立学校の正規職員に比べると業務範囲が限られることが多く、主に清掃や軽作業を担当することが一般的です。ただし、学校によっては派遣用務員でも修繕作業や設備管理を任されることがあり、業務内容が多岐にわたる場合もあります。
用務員の仕事をするために特別な資格は必要ありませんが、設備管理や修繕業務を行う際に役立つ資格があると、採用の際に有利になることがあります。例えば、第二種電気工事士の資格を持っていると、電気設備の点検や修理を行うことができ、危険物取扱者の資格があるとボイラーや燃料管理に関する業務に携わることが可能になります。また、建築物環境衛生管理技術者の資格を持っていると、学校の施設管理業務において重要な役割を果たせるため、スキルアップを目指す人にはおすすめです。ただし、これらの資格がなくても採用されることは十分に可能であり、実際に働きながら必要なスキルを身につけることもできます。
このように、用務員になるための道はいくつかありますが、公立学校で働く場合は公務員試験に合格する必要があり、私立学校や派遣会社を通じて働く場合は契約形態や待遇をよく確認することが重要です。どの雇用形態を選ぶにしても、学校の環境を維持し、安全で快適な学習環境を提供するという使命を持って働くことが求められる仕事です。
仕事を続けるか?辞めたい人の選択肢
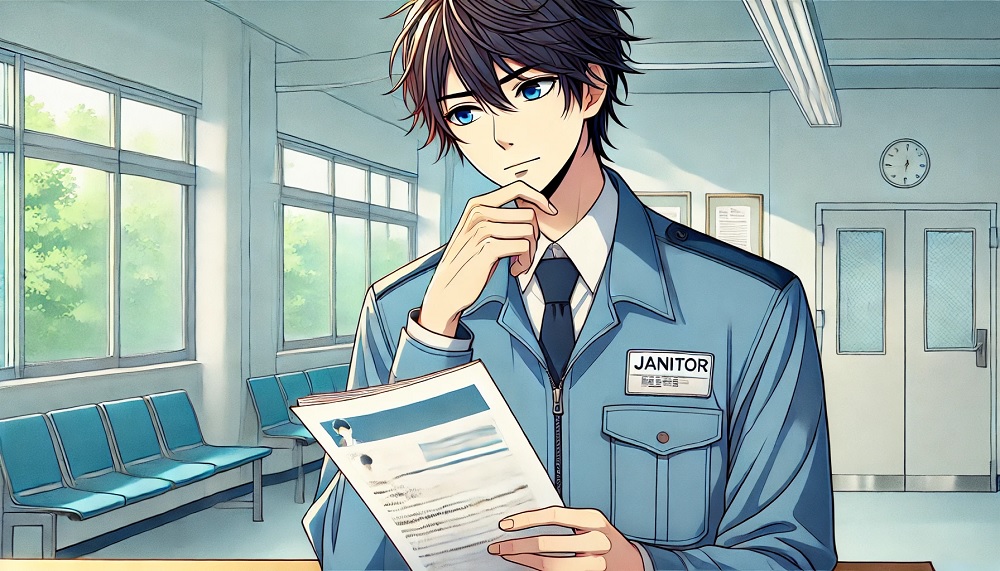
用務員の仕事を続けるべきか、それとも辞めるべきか悩んでいる人は少なくありません。仕事がきついと感じる理由は人それぞれですが、業務の多さや人間関係、給与面での不満などが主な要因となることが多いです。しかし、一方で安定した雇用や比較的規則正しい勤務体系など、メリットも多い仕事であるため、慎重に判断することが重要です。
仕事を続けるかどうかを判断する際には、まず自分が何に対して不満を感じているのかを明確にすることが大切です。例えば、業務の負担が大きいと感じている場合、具体的にどの業務が負担になっているのかを整理し、それが改善可能かどうかを検討する必要があります。人間関係に悩んでいる場合も、部署の異動や相談できる環境の有無を確認することで、解決の糸口が見つかることもあります。
給与面に不満がある場合、公立学校の正規職員であれば、勤続年数に応じて昇給があるため、長く働くことで状況が改善される可能性があります。しかし、私立学校や派遣で働いている場合は昇給の見込みが少ないことも多いため、より給与の良い職場を探すのも一つの選択肢となるでしょう。
もし仕事を辞めることを検討している場合、次の職場を見つけてから退職することが理想的です。用務員の経験は、清掃業や設備管理、ビルメンテナンスなどの職種で活かすことができます。また、資格を取得することで転職の幅を広げることも可能です。例えば、電気工事士や設備管理に関する資格を取ることで、より専門性の高い仕事に転職する道も開けます。
一方で、現在の仕事を続ける場合も、働き方を見直すことで負担を軽減できる可能性があります。例えば、効率的に業務をこなす方法を考えたり、周囲に相談して業務の分担を調整したりすることで、負担を軽減できるかもしれません。
仕事を続けるか辞めるかの選択は簡単ではありませんが、自分にとって最も良い選択肢を選ぶことが大切です。無理に続けることでストレスを溜め込むよりも、新たな道を探すことが必要な場合もあるでしょう。しかし、安易に辞めてしまうと後悔することもあるため、現状を冷静に分析し、今後のキャリアについて慎重に考えることが重要です。
用務員の仕事はきつい?業務内容と実態を総括
この記事のポイントをまとめます。
- 用務員の仕事は学校の環境維持や設備管理が中心
- 清掃や修繕、備品管理など多岐にわたる業務を担当
- 朝早くから業務が始まり、放課後まで働く
- ルーチン業務が多いが、突発的な対応も求められる
- 女性でも問題なく働けるが、一部体力を要する業務がある
- 公立学校の用務員は地方公務員として採用される
- 私立学校では契約社員やパートとして働くケースが多い
- 派遣社員として働く場合、雇用が不安定になりやすい
- 公務員の用務員は年収350万~450万円程度が相場
- 私立や派遣では年収200万~300万円程度になることが多い
- 仕事が単調に見えるが、学校運営を支える重要な役割を持つ
- 学校行事の準備や運営補助も業務の一環として行う
- 20代の若い人が少なく、採用枠が限られている
- 仕事を続けるか辞めるかは、業務負担や待遇を考慮するべき
- 転職する場合、清掃業や設備管理などの職種が活かせる